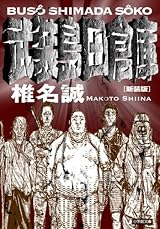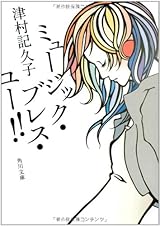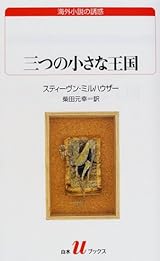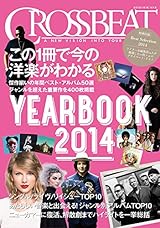作家の読書道 第155回:津村記久子さん
主に大阪を舞台に、現代人の働くこと、生活すること、成長することをそこはかとないユーモアを紛れ込ませながら確かな筆致で描き出す芥川賞作家、津村記久子さん。昨年は川端康成賞も受賞。幼い頃から本を読むのが好き、でも、10代の頃は数年にわたり、音楽に夢中で小説から遠ざかっていた時期もあったのだとか。その変遷を楽しく語ってくださいました。
その2「音楽で人生が変わる」 (2/7)
――中学生になってからは変わりましたか。
津村:ゲームばかりやって本を読まない時期が続いて、中3くらいで『ロッキング・オン』を読み始めたんです。どこの時点か分からないですけれど、中3の時にエンヤを聴いて「これや!」と思ったんかな。英語の音楽を聴けたらほぼ世界をもらったようなもののように感じました。「やっぱり音楽や!」と思って『ロッキング・オン』など洋楽系の雑誌を全部買うようになって。その頃小説はあまり読んでいないんですが、椎名誠さんはよく読んでいましたね。『あやしい探検隊』シリーズはタイトルがいいなと思って買いましたし、『武装島田倉庫』なんかも図書館で借りましたし。文体が独特なので、文章でこんなことできるんやと思っていました。他には本屋でもらう角川文庫の100冊のリーフレットに載っているものから脈絡なく選んでいました。筒井康隆さんの『農協月へ行く』はそれで読みました。でも活字といえばやっぱり音楽雑誌で、すごく字が細かいのを、隅から隅まで読んでいました。そういう時期が中3から高1くらいです。
――音楽雑誌はライターや批評家によっても文章がまったく違いますよね。
津村:こんなに自分に合う人とそうじゃない人がおるんやって思いましたね。1枚のアルバムについて3人の人がレビューを書いていると、みんな違う。こういう書き方もあるんや、と思っていましたね。小説を読むように読んでいたと思います。それこそ小学生の時に話し言葉で作文を書いて怒られたのはなんやったんやろうって思っていました。
――合う人というのは誰だったんですか。
津村:『ロッキング・オン』の兵庫慎司さんの文章がいちばん好きでした。『ミュージック・ブレス・ユー!!』の解説も書いていただいたんです。あの頃は兵庫慎司という署名があったらなんでも、エロ本の評論まで読んでいました。本当に文章の上手な方で、自分の興味のないことについても、兵庫さんの文章ならおもしろく読めるってことがすごいと思った。兵庫さんが清水義範さんや椎名誠さんのことを、コップいっぱいに水が入っているだけでそれを文章にする、というようなことを書いてはって、ああ、文章を書くってそうなんや!と思いました。この人のやっていることは、コップいっぱいの水のようななんてことない物事を、どう面白く書くかということなんやって。それで、清水義範さんの『国語入試問題必勝法』などを読みました。『主な登場人物』とか、小説の本文を読まないで登場人物説明から中身を予想するとか、むちゃくちゃなことをやっているけれど、すごく面白い試みだし、大好きで。そのだいぶ後にミルハウザーを読むようになるんですけど、もしかしたら似たようなことをやってはったんちゃうかなと思って。『バーナム博物館』の「探偵ゲーム」という、クルーというボードゲームをやっている人たちの話と、そのゲームの内容が同時進行する話にも通じるし、『三つの小さな王国』の「展覧会のカタログ」の、絵の説明だけでその画家の生涯を説明する話も同じかなと思う。そういう小説の書き方ができるんやってことは、たぶん最初に清水さんの本で学んだと思う。高校時代は『ロッキング・オン』や『クロスビート』を読み、清水さんの実験的な小説を読んでいました。
――教科書に載っているような名作などは気に入りませんでしたか。
津村:『こころ』は高1の時に読みました。角川の名作100のリーフレットに載っていたので。わたせせいぞうさんのイラストの表紙だった頃です。高2くらいはいちばん本を読まなかったですね。音楽が面白かったし、1学期のはじめにカート・コバーンが死んで、9月にオアシスの一枚目が出て。小説どころじゃなかったんです。音楽のことばかり考えていました。
――音楽のレビューは書いていましたか。
津村:めっちゃ書いてました。気持ち悪いものを。友達に自分で編集したテープを作ってあげるんですよ、その時に5ミリの方眼紙5~6枚くらいに書くんです。それが生き甲斐でした。それで、読んだ友達に「いまいち分からなかった」と言われて「そう...」みたいな(笑)。ほんま気持ち悪い、劣化コピーみたいな文章でした。あの頃の自分はエネルギーがすごかったけど、たぶんその時に出し尽くしてしまったから今わりと淡泊なことばかり書いているのかなと思います。今でもその紙を持っているという人がいるんですけど、捨ててくれ!って言ってます。気持ち悪いんですよ、本当に気持ち悪い。毎回一人ひとりに違うものを書いていたんです。それくらい言いたいことがいっぱいあったんですよ。本当にあの頃SNSとかなくてよかったです。なかったことがありがたくて仕方ない。SNSがなかったから被害を受けるのは友達だけで済んだけれど、あったらきっと知らない人にも「嫌な高校生がいる」って言われて広まっていたと思う。今、何回「気持ち悪い」って言ったんやろ。
――(笑)。自分では演奏しなかったんですか。
津村:バンドにも入っていました。コピーバンドのキーボードだったんですが、ギターの人が抜けたのでベースもやりました。最初はプリンセス・プリンセスをやって、少年ナイフやジュディ&マリーをやって。私が聴いてるようなイギリスのバンドとかは絶対やらせてもらえなかった。要するに耳コピーもできないから、スコアのあるバンドしかできなかったんです。高校の軽音なので、音楽的志向がばらばらでしたし。でも楽しかったですよ。ジュディ&マリーの最初のアルバムなんてすごくいい曲があったし。それが高2の頃です。本は1行も読んでいなかったですね。

![rockin'on (ロッキング・オン) 2015年 01月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61yqT7tWBrL._SX160_.jpg)