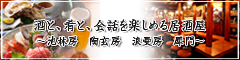1月4日(日)丁寧で豊かな本
晴れ。母親の車椅子を押して父親の墓まりと備後須賀神社に初詣。日陰となる参道は雪が凍りついていた。
実家にて仕事始め。6月刊行予定の信濃八太郎さんの『ミニシアターを訪ねて(仮)』の原稿を読む。
先日とある出版社の方から相談事のメールをいただいたのだが、そこに「『カヨと私』を拝読し、これほど丁寧で豊かな本を世に送り出された編集者」と記されており、ひどく驚いた。
私はたしかに本を作っているけれど、本は著者とデザイナーさんが作ってくれているという認識で、まさか本から私自身が評価されるとは思いもしかなったのだ。
そういえば1月に刊行する伊野尾宏之『本屋の人生』のカバーの色校を伊野尾さんのところに届けた際も、ラフを見たとある出版社の人が、「これは私には作れない装丁だ」と落ち込みつつ私を褒めていたそうだ。
それを聞いてうれしいけれど居心地が悪いというか、カバーを作ったのはデザイナーさんであり、私は素材を預けラフを見て、「これいいっすね」と言ったに過ぎないのだった。
そういえば昨年、京都の下鴨中通ブックフェスにお起こしいただいた読者の方から届いた手紙に、「背中に太陽を背負ったような方」と私のことが記されていた。
これも私は驚き、その後何度も何度も声に出して読んでみた。
私自身は太陽よりも月、いや太陽を覆い隠す翳りあるどす黒い雲のような存在だと思っていたのだが、外から見るとまったく違うらしい。
編集仕事にしてもいつもアップアップで慌てて本を作っている認識だったのだが、それが「丁寧で豊か」に見えるとは自己評価と外部評価が著しく異なるものの、外部評価が高いのならばそれをエベレスト登頂のように目指すべきだろう。
というわけで手紙をいただいたその日から「背中に太陽を背負ったような」人間になろうと努力しているのだが、本作りにおいてはこれから「丁寧で豊かな本」を目標にしようと誓った。
信濃八太郎さんの『ミニシアターを訪ねて(仮)』は、まさしくそういう本になりそうで、うれしく原稿を読む。